【アートな小部屋・春宵一刻】
サステナブルな視点を持った人たちが、アート、本、映画などについて語る小部屋。
「春の夜は雅趣に富み、そのすばらしさは千金に値するもの」という意から、
この小部屋を訪れた皆さんのひとときがそうあってもらえたらと願っています。
「夏が来れば 思い出すはるかな尾瀬 とおい空〜」
という一節が童謡にあるが、日本国民にとって今年の忘れられない思い出は、間違いなく一年遅れの東京オリンピックというところだろうか。
先日、私にとって「忘れられない夏」が蘇る出来事があった。私は苫小牧生まれの苫小牧育ち。港町である。夏には「港まつり」という夏の風物詩がある。幼い頃、その時期になると毎年祖母に”履物屋”に連れて行かれた。この履物屋で浴衣用の「下駄」を新調してくれたのだ。赤い鼻緒・桜柄・金魚もあったな。祖母に手を引かれ毎年行った履物屋。苫小牧の小さな繁華街にあった履物屋。そこで祖母が嬉しそうに私に下駄を選んでくれた。帰ったら母が私の髪を結い、浴衣を着せてくれた。夜はその新調した下駄を履いて、盆踊りに”わたあめ”だ。
そんな今でもまるでその時の匂いが溢れてくる瞬間を、ある日新聞の片隅で感じた。
「いとう履物店115年に幕を」
思い出の履物屋さんが閉店するという。オーナーご夫婦が老齢でこれ以上の継続は無理だと判断したそうだ。日本各地からのリピーターも多数。継続を望む声も多いという。なぜなら、このご時世、下駄の鼻緒をつけられる職人さんはほとんどいないという。鼻緒職人も少なくなったそうだが、それでも毎年新しい柄が用意され、今年は鬼滅柄が人気だったというから驚きだ。
話を戻そう。私は、新聞を読み、居ても立っても居られなくなり、その店に駆けつけ、昔のように下駄を買った。外観も店内もほとんど当時のままだ。閉店は6月からご案内していたそうで店内にはほとんど商品がなくなっていた。閉店を知った多くのお客様が早々と駆けつけ購入していったそうだ。私は、しみじみ当時の思い出し、店内を懐かしんだ。まるで私の横に祖母がいるように。奥様は昔ながらの気立ての良い方で、「昔の鼻緒はよく切れたけれど今の鼻緒は丈夫で切れることがないのよ。昔はね、鼻緒がすぐ切れるから手ぬぐいを破って、みんなが自分で鼻緒をつけていたけれどね」と笑顔で教えてくれた。私は、その言葉を聞きながら、そういえば樋口一葉の「たけくらべ」に鼻緒が切れる有名な切ない恋の場面があったな…と思い出した。若い不器用な二人の恋の思いを密かに確認する絶妙な場面だ。
走馬灯のように祖母や母と過ごした夏の一風景を思い出しながら、現在のような便利な世の中は人を間違いなく幸せにするが、逆に、そんな切ない恋の話が生まれることもないのかも…と、履く予定のない下駄を受け取り、一人小さく笑った。いつの時代も思い出が人の心の灯火であって欲しいなと感じながら。
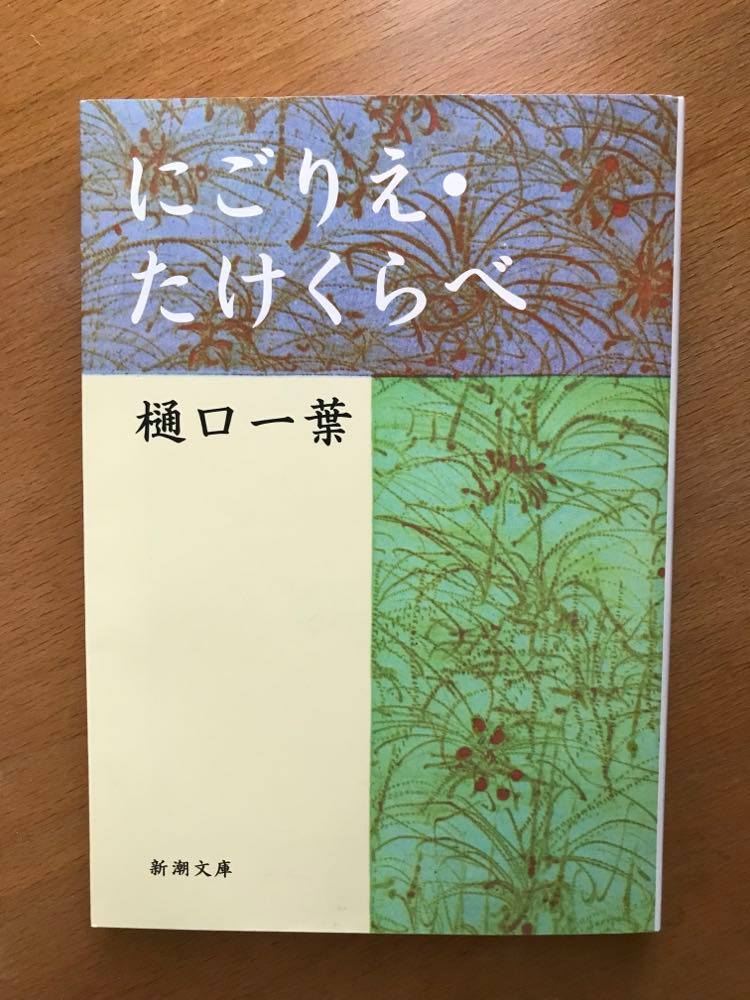
書いた人/Masae Kawaminami
夢は、「人生がアートな世界」になること。アートとは感動であり、五感に響くすべてがアートと捉え、それが欠けた人生は無味乾燥だと考える。自他ともに認める無類の本好きで、映画・音楽・舞台への造詣も深い。どんな環境にいても、アートが人の心の拠り所であってほしいと願い、コラムを執筆。北海道在住。







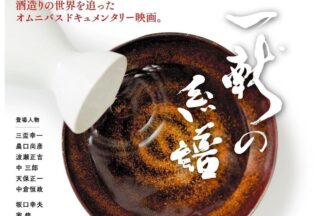


この記事へのコメントはありません。